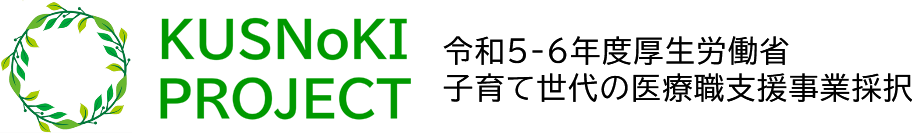KUSNoKIプロジェクトメンバーからのごあいさつと、いただいた応援メッセージをご紹介します。

ごあいさつ

KUSNoKIプロジェクト 実施責任者
京都大学医学研究科
医学教育・国際化推進センター
教授
片岡 仁美
Hitomi Kataoka

KUSNoKIプロジェクト
医学研究科担当
京都大学医学研究科
医学教育・国際化推進センター
助教 時信 亜希子
Akiko Tokinobu

KUSNoKIプロジェクト
医学部附属病院担当
京都大学医学部附属病院
総合臨床教育・研修センター
特定助教(医師の働き方改革担当)
村田 亜紀子
Akiko Murata
応援メッセージ

京都大学医学研究科
医学研究科長 伊佐 正
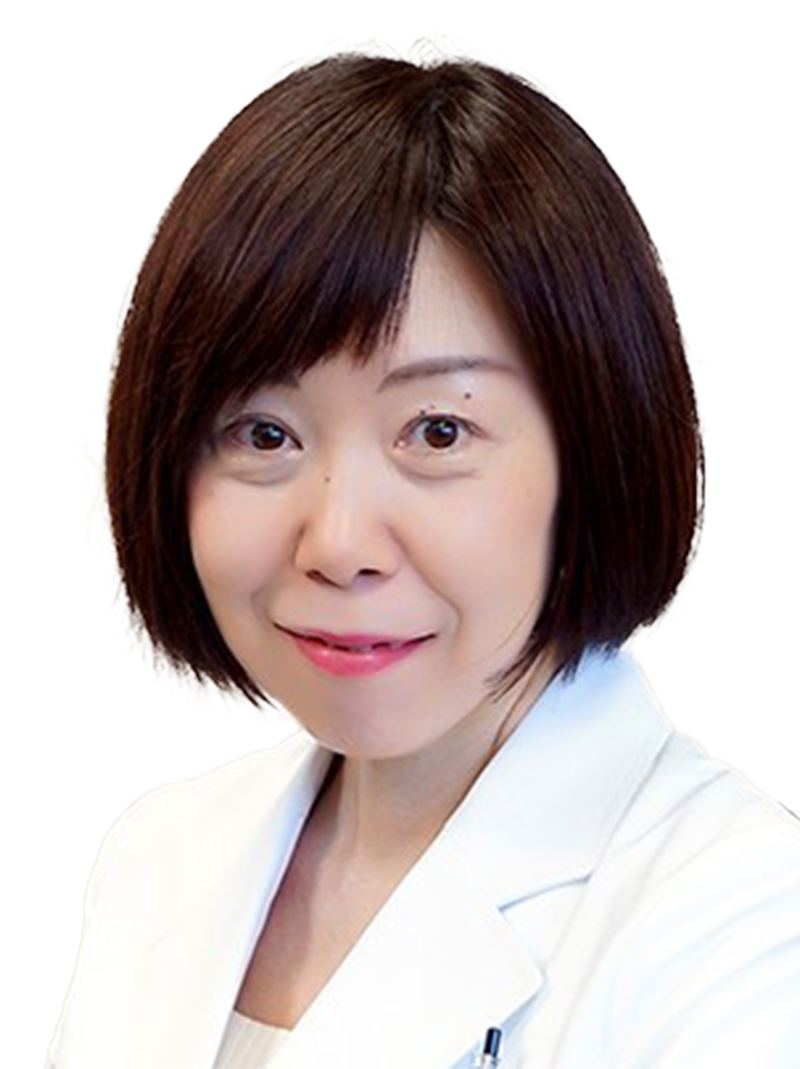
京都大学医学研究科
医学研究科長補佐 柳田 素子
(男女共同参画担当)

京都大学医学部附属病院
病院長 髙折 晃史

京都大学医学部附属病院
副病院長 溝脇 尚志
(教育、人事、男女共同参画推進担当)

京都大学医学部附属病院
副病院長 松田 秀一
(診療、労務、病床管理担当)
ごあいさつ
京都大学では、男女共同参画推進センターが設置され、様々な復職支援、育児支援に全学的に取り組み、男女共同参画に取り組んできました。また、京都大学医学部附属病院においては、いち早く病児保育施設(現在は病後児保育室として運営)を開室するとともに、柔軟な働き方を可能とするキャリア支援診療医制度を2016年度から導入、26時間保育やお迎え保育などの子育て世代を支援する病院としての取り組みにも積極的に取り組んできました。さらに、2024年度から新しい院内保育所も開設され、育児支援・キャリア支援の機運が一層高まっている状況です。
このようななか、昨年に続き厚生労働省2024年度子育て世代の医療職支援事業に採択頂き、プロジェクトとして子育て世代の医療職支援に取り組む機会を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。
プロジェクト名は京都大学のシンボルであるクスノキをモチーフにKUSNoKI(Kyoto University hospital Supporting Network of Keeping up career and Innovation)プロジェクトとしました。クスノキは長い時間をかけて着実に大木へと生長することが特徴とされますが、本プロジェクトもそれぞれの人に寄り添う存在として着実な成長を重ねていきたいと願っています。

KUSNoKIプロジェクト 実施責任者
京都大学医学研究科
医学教育・国際化推進センター
教授 片岡 仁美
Hitomi Kataoka
KUSNoKIプロジェクト発足メンバーとして2023年10月よりプロジェクトに関わらせていただいております。
前職の岡山大学病院ダイバーシティ推進センターでは、片岡仁美教授のご指導のもと、MUSCATプロジェクトのスタッフとして医療人のキャリア支援や各種トレーニング、セミナー開催、育児支援など様々な活動に携わっていました。この経験を活かして、京都大学においても片岡仁美教授とともにKUSNoKIプロジェクトの活動に日々取り組んでいるところです。
私自身は医療職ではなく、医療職の皆様の真のニーズに対して配慮が足りていなかった点があるかもしれませんが、今後は2024年度より参画された村田亜紀子特定助教とダブルAKIKOとして手を携え、それぞれ病院担当(村田)、研究科担当(時信)として、プロジェクトの活性化に向けて取り組む所存です。一例としては、プロジェクトのイベントや各種サービス・プログラムを利用者の方々に快く利用していただくための方策として、アンケート解析を行い、利用される医療職の方々が抱える問題点やその要因を探り、改善・向上につなげていくことを目標にしています。今後ともご意見・ご要望をお寄せいただけますと幸いです。皆様にとって心地よいワーク・ライフを提供できるプロジェクトの一助となれるようがんばっていきたいと考えております。何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

KUSNoKIプロジェクト 医学研究科担当
京都大学医学研究科
医学教育・国際化推進センター
助教 時信 亜希子
Akiko Tokinobu
2023年に医学系研究科を主体として始動したKUSNoKIプロジェクトは、2024年度よりKUSNoKIプロジェクトの京都大学医学部附属病院の窓口ができ、活動をより拡げられる体制になりました。
私は岡山県での勤務時、学位取得や学会企画参加に際し岡山県医師会や学会等の支援制度を利用したことがあり、当事者として、そして支援担当者として女性医師支援やDE&I(Diversity, Equity and Inclusion)に関わるプロジェクトの重要性と存在意義を実感してきました。京都大学でも片岡仁美教授のご指導のもと、引き続きこうした活動に関われることが嬉しく、やりがいを感じています。
時代の変化とともに、女性だけをとりあげて支援するのはどうなのか、ほかの属性についても考えるべきではという話が出るようになり、ダイバーシティの対象は拡大してきました。このことは喜ばしいことである反面、それぞれに対する施策や意識改革が不十分なまま焦点がぶれやすくなっており、女性支援を終わりにできるほどの状況には残念ながら至っていません。これまでなされていたような支援だけではDE&Iがむしろ停滞する可能性すら出ており、こうした情勢を意識した、長期的な視野に基づく取り組みがより必要とされているように感じています。
知見を日々広げ、深めながら、KUSUNoKIプロジェクトの4本の柱である、キャリア形成支援、両立支援、復職支援、普及啓発支援を軸にした取り組みを進め、“女性支援”などとわざわざとりあげなくても、誰もが自分らしく働いていける医療界を作っていけるよう、京都から発信していけたらと考えております。
みなさまのワーク・ライフがより自分らしく心地よいものになりますよう、ともに成長する存在になれるよう尽力したいと思っていますので、何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

KUSNoKIプロジェクト 医学部附属病院担当
京都大学医学部附属病院
総合臨床教育・研修センター
特定助教(医師の働き方改革担当)
村田 亜紀子
Akiko Murata
応援メッセージ
京都大学では2022年度から「京都大学男女共同参画推進アクションプラン」を掲げ、女性教員の増加に取り組んでいます。一方、医学部医学科だけに注目しますと、教授の66名中7名が女性であり、近年特にその比率が上昇しています。2023年11月には女性教授座談会を開催し、若手医師・研究者の支援とともに、学生の意欲や夢をさらに後押しするための支援の基盤づくりについても活発な意見が出されました。その概要については同窓会誌の新年号および研究科ホームページに掲載しております。
従来本学では男女共同参画センターが女性研究者支援に取り組んできた歴史があります。さらにダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進の一環として、2023年12月、京都大学の教職員を対象に、小学1年生から6年生までを預かる学童保育所である京都大学キッズコミュニティ(KuSuKu)がオープンするなど、一層のDE&Iに取り組んでいます。昨年度に引き続き2024年度厚生労働省子育て世代の医療職支援事業への採択を機に、男女、職種を超えて誰もが活躍する基盤づくりが一層進んでいくことを祈念しています。

京都大学医学研究科
医学研究科長 伊佐 正
本学では「京都大学男女共同参画推進アクションプラン」を策定し、2027年度に全学の女性教員比率を20%、役員会構成員の女性比率を25%とすることを目標としております。
本学では男女共同参画センターを中心に女性研究者支援の取り組みを進めてきましたが、医学研究科においても独自の取り組みを進めています。育児中の教員の業務負担を軽減、保育室、授乳スペースを充実に加えて、女性研究者や学生支援のための情報サイトも充実させています。2023年の京都大学キッズコミュニティ(KuSuKu)の開所、2024年の院内保育所開所など子育て支援の機運が高まる中、昨年に続き2024年度厚生労働省子育て世代の医療職支援事業が研究科と病院の枠組みを繋ぐような取組として発展することを願っています。
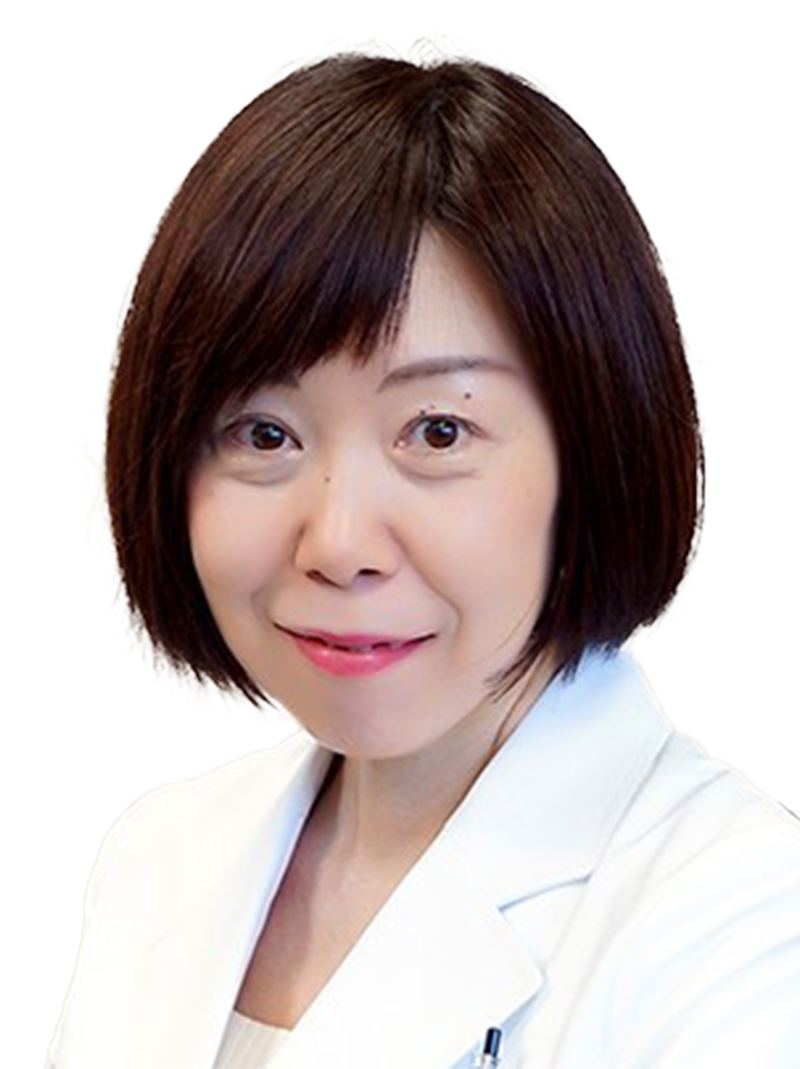
京都大学医学研究科
医学研究科長補佐 柳田 素子
(男女共同参画担当)
京大病院は、大学病院の使命である「診療・研究・教育」に関する3つの基本理念「患者中心の開かれた病院として、安全で質の高い医療を提供する」「新しい医療の開発と実践を通して、社会に貢献する」「専門家としての責任と使命を自覚し、人間性豊かな医療人を育成する」をベースに、「安心・安全な医療の提供」に努めています。
我々のミッションを果たすべく邁進しつつ、病院で勤務する医療職のキャリア構築やダイバーシティの推進も重要視しています。女性教員の比率向上を目的にキャリア支援診療医制度やプラスワン制度を導入しています。丁度2024年には新たな院内保育所の開園も実現したタイミングで、昨年に続き2024年度厚生労働省子育て世代の医療職支援事業に採択頂いたことはさらに当院の取り組みの追い風になります。今後も一層の発展を目指したいと思います。

京都大学医学部附属病院
病院長 髙折 晃史
優れた医療従事者を育成することは、京都大学医学部附属病院の3つの基本理念の一つであり当院の大きな使命です。人材育成の観点からは、本人の高い意欲とともにそれを支える環境も重要です。医療従事者が生涯成長を続けるためにはワークライフインテグレーション(仕事とプライベートの双方が相乗する)の考え方に基づく環境整備が求められます。
京都大学医学部附属病院ではそのような考え方のもと院内保育所「きらら」を2008年に開所し、2016年から平日は毎日「お迎え&託児」サービスを提供、夜間保育も週1回実施してきました。院内保育園は2024年に新体制で開所し、さらなる充実が実現しています。また、病院建物内に設置された病児保育室「こもも」は京都大学男女共同参画センターによって運営され、現在は病後児保育室として運営しております。
厚生労働省子育て世代の医療職支援事業の採択を契機に、医学部・医学研究科・病院が連携して働き方改革にも対応しつつ優れた医療従事者の育成に取り組んでいきたいと思います。

京都大学医学部附属病院
副病院長 溝脇 尚志
(教育、人事、男女共同参画推進担当)
2024年に医師の時間外労働の上限規制が始まり、当院でも医師の働き方改革に病院を挙げて取り組んできました。働き方改革と多様な人材が活躍することは両輪の取り組みです。病院として育児世代の医療人が働きやすくなることは働き方改革の観点からも大変重要です。
KUSNoKIプロジェクトは育児世代の医療人の多面的な支援を行うものですが、男女問わず育児世代が直面する課題を抽出し、それに対して積極的な改善策を見つけ、ともに取り組む本プロジェクトは、働く人に寄り添う存在となれるのではないかと期待します。
また、現場の課題に取り組むことで、より本質的な働き方の改善にもつながることを願っています。

京都大学医学部附属病院
副病院長 松田 秀一
(診療、労務、病床管理担当)